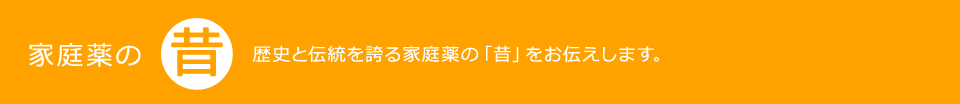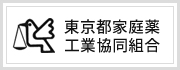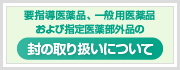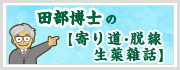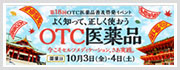日野百草丸発売開始年:昭和20年代
江戸時代から時を越えて伝承された胃腸薬「百草丸」
伝統的であっても新しい生薬製剤です

万病に効く腹薬
日野製薬の前身日野屋は、江戸時代に中山道木曽藪原宿で創業し、霊峰木曽御嶽の「御霊薬(ごれいやく)」とも称された民間伝承薬「百草」を販売してまいりました。
「百草」は、キハダの内皮(生薬:オウバク)を乾燥・裁断し、水で煮出して煮詰めたエキスを板状にした単味の生薬製剤です。下痢を伴う胃腸の症状を改善します。有効成分の塩化ベルベリンには抗菌作用があり、昔は「万病に効く腹薬」「腹痛の妙薬」とも呼ばれ、風邪、赤痢、皮膚病、外傷、眼病、口内炎などに幅広く用いられました。竹の皮に包まれた「百草」は、御嶽登拝の信者や木曽路を行き来した旅人の土産品として全国に普及した胃腸薬です。
木曽の自然と生活の中から生まれた百草
かつて木曽御嶽山麓は薬草の宝庫であり、「百草」は、木曽御嶽開山の修験者がキハダの内皮を煎じて薬とすることを村人に伝えたのが始まりといわれています。木曽の厳しい自然環境の中で人々はキハダを採取し、自らの健康管理のための常備薬としたり、土産品として販売し生活を営んできました。又生計を維持するため大切にされた農耕馬への処方例も記録として残っています。戦時中には兵隊さんの慰問袋に入れられ衛生状態の悪い外地での下痢止め薬としてあるいは胃腸の健康状態を保つためにも役立てられました。
百草丸の誕生(昔も、今も、これからも)
昭和22(1947)年、第10代11代日野屋当主の日野文平が日野製薬を設立し、苦味健胃生薬「オウバク」を主成分とする「百草丸」・「奇応丸」・「普導丸」など数々の生薬製剤を開発・発売してまいりました。
平成27(2015)年には、従来の百草丸に粘膜修復成分を加えた新百草丸「百草丸プラス」を、平成28(2016)年には、効き目はあっても飲みにくかった民間伝承薬の「百草」の錠剤化に成功し「百草錠」を発売いたしました。そして令和元年(2019)年、新しい「日野百草丸」を発売しました。
「百草丸」は、長年にわたって培ってきた独自の製造技術を活かして作り上げた伝統的で新しい現代人のための胃腸薬です。
良薬は口に苦し
自然の産物である生薬オウバクは、「良薬は口に苦し」の言葉にある通り、苦味や香りが味覚や嗅覚を刺激して消化管運動を活発にする健胃生薬です。服用の際には、この生薬特有の苦味と香りを感じることが大切で、当社の百草丸は、あえて、オウバクから製したオウバクチンキを二次コーティングし製品として仕上げています。通常の丸剤の場合には一次コーティングを施し完成品としますが、薬効を丸剤の中に閉じ込めてしまわないように天然の生薬の効果を服用直後に感じることで無理なく胃腸の働きが高められるように工夫した当社独自の製造方法で作り上げた製剤です。
民間伝承薬を後世につなぐ
長い歴史を持つ「民間伝承薬」は、人類の経験に基づき導き出され現代まで受け継がれてきた薬で、現代医療だけでは完治しきれない、あるいは、緩和ケアーを必要とする疾患に対して補助的に用いる薬としても見直されています。病気の予防や疾患の治療および予後の健康維持に活用していただくのに適しており、また、「自らの体は自ら守る」というセルフメディケーションに役立てていただくのにも適した薬といえます。木曽の歴史と風土に育まれてきた「百草・百草丸」等の生薬製剤を後世に伝えていくために、自然の生薬そのものの良さを活かした製剤技術を探求し、伝統を踏まえながらも新しい製品づくりに努めてまいります。
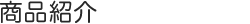
商品の特徴
- 日野百草丸は七種類の生薬を配合した胃腸薬です。胃弱、胃もたれ、胸やけ、食べ過ぎ、飲み過ぎ、消化不良などの症状を改善します。
健胃生薬のオウバクエキス、ビャクジュツ末、ガジュツ末、リュウタン末、センブリ末、便通を整える整腸生薬のゲンノショウコ末、さらに新たに、粘膜を保護し修復する粘膜修復生薬のエンゴサク末を配合し、これらの「健胃」・「整腸」・「粘膜修復」の三つの働きにより、胃腸の調子を整え、不快な症状を改善し、健康な胃腸へと導きます。
生活習慣やストレスや加齢などによる胃腸の不調にお困りの方、胃腸トラブルになり易く長引いている方に、常備薬としてお備えいただき、症状に応じて食前又は食後に服用いただくことをおすすめします。
| 第2類医薬品 ※パッケージは変更する場合がございます。 | |
| 商品名 | 日野百草丸 |
|---|---|
| 効能・効果 | 食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐 |
| 用法・用量 |
|
| 成分・分量 |
|
| 商品構成 | ビン入:480粒、1020粒、2460粒 袋入:7800粒(3900粒×2袋) 分包タイプ:20粒×12 包 |
※使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお飲みください。
商品に関する詳細情報は、日野製薬株式会社の企業サイトで、ご確認ください。